目次
はじめに
日本政策金融公庫は、中小企業の海外展開を支援するため、積極的に海外拠点の展開を進めています。グローバル経済が急速に発展する中、日本の中小企業が海外市場に進出することは、事業成長と競争力向上のために不可欠な戦略となっています。
海外展開支援の重要性
現代の経済環境では、国内市場の縮小や少子高齢化の影響により、多くの中小企業が新たな成長機会を海外に求める必要に迫られています。日本政策金融公庫は、このような企業のニーズに応えるため、海外駐在員事務所の設置を通じて、現地での情報提供や相談サービスを強化しています。
海外展開は単なる販路拡大にとどまらず、技術革新や経営革新の機会を提供します。現地の市場特性を理解し、適切な戦略を立てることで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
グローバル化への対応
日本政策金融公庫の海外支援体制は、単独での海外進出が困難な中小企業にとって重要な橋渡し役となっています。現地の法規制や商慣習、市場動向などの情報提供を通じて、企業のリスクを軽減し、成功確率を高める役割を果たしています。
特に、言語や文化の違い、現地パートナーの選定など、海外展開特有の課題に対して、専門的なアドバイスやサポートを提供することで、中小企業の国際競争力向上に貢献しています。
支援の包括性
日本政策金融公庫の海外展開支援は、資金調達から現地での事業運営まで、包括的なサポートを提供しています。融資制度だけでなく、セミナーの開催や情報提供を通じて、企業の海外展開を多面的に支援する体制を構築しています。
この包括的なアプローチにより、企業は海外展開の各段階で必要なサポートを受けることができ、より確実で持続可能な国際事業を展開することが可能となります。
海外駐在員事務所の展開状況

日本政策金融公庫は、アジア地域を中心に海外駐在員事務所を戦略的に配置し、中小企業の海外展開を現地でサポートしています。現在、3つの主要拠点を設置し、それぞれの地域特性を活かした支援体制を構築しています。
上海駐在員事務所(中国)
中国の上海駐在員事務所は、日本政策金融公庫の海外展開の先駆けとなる重要な拠点です。中国は日本の中小企業にとって最大の海外市場の一つであり、製造業を中心に多くの企業が進出しています。上海事務所では、現地の法規制の変更や市場動向の情報提供、現地パートナー企業の紹介などを通じて、日本企業の中国事業をサポートしています。
特に、中国特有のビジネス慣習や規制要件について、専門的なアドバイスを提供することで、企業のコンプライアンスリスクを軽減し、安定した事業運営を支援しています。また、現地の金融機関や商工会議所との連携により、包括的な支援ネットワークを構築しています。
バンコク駐在員事務所(タイ)
タイのバンコク駐在員事務所は、東南アジア地域への展開拠点として重要な役割を果たしています。タイは政治的安定性と整備されたインフラにより、多くの日本企業が製造拠点や地域統括拠点として活用している国です。バンコク事務所では、製造業だけでなく、サービス業や小売業など、幅広い業種の企業支援を行っています。
タイ政府が推進するEEC(東部経済回廊)などの経済政策についての最新情報提供や、現地での投資機会の紹介を通じて、企業の戦略的な事業展開を支援しています。また、ASEAN域内での事業拡大を検討する企業に対して、地域全体の市場分析や進出戦略のアドバイスも提供しています。
ホーチミン駐在員事務所(ベトナム)
2023年11月に新設されたホーチミン駐在員事務所は、急成長するベトナム市場への日本企業の進出を支援する最新の拠点です。ベトナムは若い労働人口と安定した経済成長により、製造業の新たな拠点として注目を集めています。ホーチミン事務所では、現地の労働法規や投資環境についての情報提供を重点的に行っています。
特に、ベトナム政府が進める工業化政策や外国投資優遇制度について、最新の情報を提供することで、企業の投資判断をサポートしています。また、現地の人材確保や工場建設に関する実務的なアドバイスも提供し、企業の円滑な事業立ち上げを支援しています。
今後の拠点展開計画
日本政策金融公庫は、現在の3拠点に加えて、さらなる海外展開を検討しています。特に、インドネシア、インド、メキシコなど、日本企業の関心が高い市場への拠点設置が期待されています。これらの新興市場では、現地の規制環境や商慣習が複雑で、専門的なサポートが不可欠となっています。
将来的には、デジタル技術を活用したリモート支援サービスの充実により、物理的な拠点を設置していない国・地域でも、効果的な支援を提供する体制の構築を目指しています。これにより、より多くの中小企業が海外展開の機会を活用できるようになることが期待されています。
海外展開支援融資制度の詳細
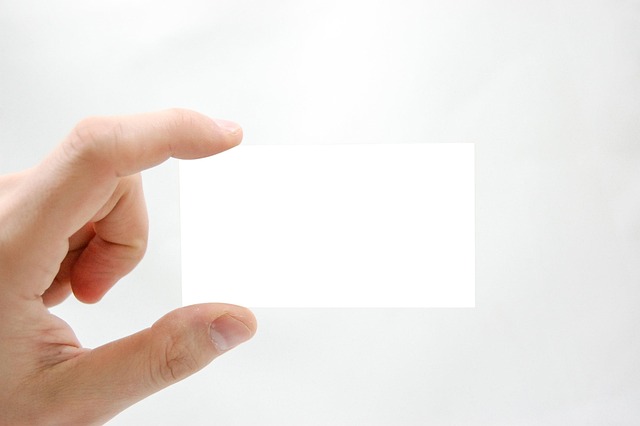
日本政策金融公庫は、中小企業の海外展開を資金面からサポートするため、「海外展開・事業再編資金」をはじめとする包括的な融資制度を提供しています。これらの制度は、企業の海外展開の各段階に応じて柔軟に活用できるよう設計されています。
融資限度額と資金使途
海外展開・事業再編資金では、直接貸付の場合は最大14億4千万円、代理貸付では1億2千万円という大規模な融資限度額を設定しています。この資金は、海外での工場建設や設備導入などの設備資金から、現地での運転資金まで幅広い用途に活用できます。特に製造業では、現地での生産設備投資に大きな資金が必要となるため、この高い融資限度額は企業の本格的な海外展開を可能にします。
また、海外市場開拓のための専用制度では、最大7,200万円(うち運転資金4,800万円)の融資を受けることができます。この制度は、海外での販路開拓や現地法人設立など、比較的規模の小さい海外展開から始める企業に適しており、段階的な海外進出を支援しています。
返済条件と利率設定
返済期間は、設備資金については20年以内、運転資金については7年以内と、企業の投資回収期間を考慮した柔軟な設定となっています。設備資金の長期返済期間は、海外での工場建設や大型設備投資における投資回収の長期性を考慮したものです。特別な事情がある場合には、返済期間の延長も可能であり、企業の事業計画に応じた柔軟な対応を行っています。
利率については、基準利率(上限2.5%)が基本となりますが、EPA/FTA締結国での展開や一定の要件を満たす場合には特別利率が適用されます。これにより、政府が推進する経済連携協定の活用を促進し、企業の国際競争力向上を支援しています。
融資対象となる企業要件
融資対象となる企業は、経営上の必要性から海外展開を行う中小企業で、いくつかの要件を満たす必要があります。主な要件として、事業の延長性、本邦内での事業拠点の存続、経営革新の一環としての海外市場開拓などが挙げられます。これらの要件は、企業の海外展開が国内事業の単純な移転ではなく、事業全体の成長につながることを確保するためのものです。
また、経済構造の変化に対応するための海外展開、海外事業の再編、海外事業の業況悪化への対応なども支援対象となります。これにより、新規の海外進出だけでなく、既存の海外事業の改善や再構築も支援し、企業の持続的な国際事業展開を促進しています。
担保・保証の取り扱い
担保や保証人については、企業の希望や財務状況に応じて柔軟に相談できる体制を整えています。海外展開では、国内での担保提供が困難な場合も多いため、企業の事業計画や将来性を重視した審査を行い、必要に応じて無担保・無保証での融資も検討します。
特に、技術力や市場性に優れた企業については、担保に過度に依存せず、事業の成長性や収益性を重視した融資判断を行っています。これにより、従来の担保主義では支援が困難だった革新的な中小企業の海外展開も積極的にサポートしています。
地域別支援体制とネットワーク

日本政策金融公庫は、全国各地の支店網を活用して、地域の中小企業の海外展開を支援しています。各地域の産業特性や企業ニーズに応じたきめ細かいサポートを提供し、地方企業の国際化を促進しています。
関東地域の支援体制
神奈川県、東京都、埼玉県、千葉県を中心とした関東地域では、製造業から IT 企業まで多様な業種の企業が海外展開を目指しています。横浜市や川崎市では港湾機能を活かした貿易関連企業、東京23区では金融・IT サービス企業、埼玉県や千葉県では製造業の海外展開が活発です。各支店では、地域の産業特性を踏まえた専門的なアドバイスを提供しています。
特に、東京都心部では高度な技術やサービスを持つ企業が多く、これらの企業の海外展開では知的財産権の保護や現地でのブランド展開が重要な課題となります。関東地域の支店では、こうした高付加価値企業の特殊なニーズに対応した支援を行っています。
地方都市での海外展開支援
函館支店をはじめとする地方都市の支店では、地域の特色ある産業の海外展開を支援しています。函館支店では、水産業や食品加工業などの地域基幹産業の海外市場開拓を重点的に支援し、セミナーの開催や現地視察の企画などを通じて、企業の海外展開への理解を深める取り組みを行っています。
地方企業の海外展開では、限られた経営資源の中で効果的な国際化を進める必要があります。そのため、地方支店では、複数企業による共同での海外展開や、地域商社機能を活用した輸出促進など、地方企業に適した海外展開モデルの提案も行っています。
きらぼしグループとの連携
日本政策金融公庫は、きらぼしグループとの覚書締結により、双方のネットワークを活用した海外展開支援体制を強化しています。この連携により、地方銀行の地域密着性と政府系金融機関の専門性を組み合わせた、より効果的な支援が可能となります。
きらぼしグループとの連携では、海外拠点間の情報共有や現地での企業紹介、合同でのセミナー開催などを通じて、中小企業により質の高いサービスを提供しています。また、両機関の顧客企業間のビジネスマッチングも促進し、海外での事業機会の拡大を支援しています。
支援機関との協力体制
各地の商工会議所、商工会、中小企業支援センターなどの支援機関と連携し、地域全体での海外展開支援体制を構築しています。これらの機関との連携により、企業発掘から事後フォローまで、一貫した支援を提供できる体制を整えています。
支援機関との協力では、海外展開セミナーの共同開催、現地視察団の組成、海外バイヤーとの商談会開催など、様々な形での協力を行っています。これにより、個別企業だけでは困難な海外市場へのアプローチも、地域全体の取り組みとして実現できるようになっています。
セミナー・相談サービスの活用

日本政策金融公庫は、融資だけでなく、セミナーの開催や個別相談を通じて、中小企業の海外展開に関する知識向上と意識啓発を図っています。これらの教育・啓発活動は、企業の海外展開成功率を高める重要な役割を果たしています。
海外展開セミナーの内容と特徴
各支店で開催される海外展開セミナーでは、アジア各国をはじめとする主要市場の特性、進出時の留意点、現地でのビジネス慣習などについて、実務的な情報を提供しています。セミナーでは、実際に海外展開を成功させた企業の事例発表も行われ、参加者は具体的なノウハウや課題解決方法を学ぶことができます。
特に函館支店で開催されたセミナーでは、中小企業者や支援機関関係者が多数参加し、海外展開への関心を高める機会となりました。こうしたセミナーは、単なる情報提供にとどまらず、参加企業間のネットワーキングの場としても機能し、企業同士の連携による海外展開も促進しています。
個別相談サービスの充実
各支店の中小企業事業の窓口では、企業の個別事情に応じた詳細な相談サービスを提供しています。海外展開の検討段階から実際の進出後のフォローアップまで、企業の成長段階に応じた継続的な支援を行っています。相談では、市場調査の方法、現地パートナーの選定、法的手続き、資金計画など、海外展開の全般にわたってアドバイスを提供しています。
個別相談では、企業の業種や規模、海外展開の目的に応じて、最適な進出先や進出方法を提案します。また、企業が直面する具体的な課題に対して、海外駐在員事務所からの最新情報や、他の成功企業の事例を活用した実践的なソリューションを提供しています。
デジタルツールを活用した情報提供
従来の対面でのセミナーや相談に加えて、オンラインでの情報提供サービスも充実させています。ウェビナーの開催により、地理的制約を受けずに多くの企業がセミナーに参加できるようになりました。また、海外市場の最新情報や規制変更について、メールマガジンやウェブサイトを通じて迅速に情報提供を行っています。
デジタルツールの活用により、企業は自社の都合に合わせて情報収集や相談を行うことができ、海外展開の検討がより身近なものとなっています。また、過去のセミナー資料や相談事例のデータベース化により、企業が必要な時に必要な情報にアクセスできる環境を整えています。
フォローアップ体制の強化
セミナー参加後や相談後の企業に対して、継続的なフォローアップを行い、実際の海外展開につなげる取り組みを強化しています。定期的な状況確認や追加の情報提供により、企業の海外展開計画の具体化を支援しています。
フォローアップでは、企業の海外展開の進捗に応じて、融資制度の紹介、現地パートナーの紹介、関連企業との引き合わせなど、具体的なサポートを提供します。これにより、セミナーや相談が単発の情報提供に終わらず、実際の事業成果につながるよう支援しています。
今後の展望と課題

日本政策金融公庫の海外展開支援は、急速に変化する国際経済環境に対応しながら、さらなる充実を図っています。デジタル化の進展や新興国市場の拡大など、新たな機会と課題に対応した支援体制の構築が求められています。
デジタル化時代への対応
デジタル技術の急速な発展により、中小企業の海外展開の形態も大きく変化しています。EC サイトを通じた越境取引、デジタルマーケティングによる海外顧客開拓、リモートでの海外事業管理など、従来とは異なる海外展開モデルが登場しています。日本政策金融公庫では、こうした新しい海外展開形態に対応した支援制度の検討を進めています。
特に、IT 関連企業やデジタルサービス企業の海外展開では、従来の製造業とは異なる課題やニーズがあります。知的財産権の国際的保護、データ保護規制への対応、現地でのデジタルインフラの活用など、デジタル時代特有の課題に対応した専門的な支援体制の構築が急務となっています。
新興国市場への対応強化
アフリカ、南米、東欧など、これまで日本企業の進出が限定的だった新興国市場への関心が高まっています。これらの市場では、高い成長性がある一方で、政治的リスクや為替リスク、インフラの未整備など、特有のリスクも存在します。日本政策金融公庫では、こうした新興国市場への進出を検討する企業に対して、より専門的なリスク評価と支援を提供する必要があります。
新興国市場での事業展開では、現地の社会情勢や文化的背景の理解が特に重要となります。そのため、現地の専門機関や国際機関との連携を強化し、より深い市場理解に基づいた支援を提供していく計画です。
サステナビリティへの対応
ESG(環境・社会・ガバナンス)への関心の高まりにより、海外展開においてもサステナビリティへの配慮が不可欠となっています。現地での環境負荷軽減、労働環境の改善、地域社会への貢献など、持続可能な海外事業の展開が求められています。日本政策金融公庫では、こうしたサステナビリティ要素を考慮した海外展開支援の仕組みを検討しています。
特に、再生可能エネルギー関連企業や環境技術企業の海外展開については、各国の環境政策や国際的な環境協定との整合性を考慮した支援が重要となります。これらの企業の海外展開は、日本の技術力の国際的な発信と同時に、地球環境問題の解決にも貢献する重要な取り組みです。
人材育成と能力向上
海外展開を成功させるためには、国際的な視野を持った人材の育成が不可欠です。しかし、多くの中小企業では、海外事業に精通した人材の確保が困難な状況にあります。日本政策金融公庫では、企業の人材育成を支援するため、海外研修制度や専門家派遣制度の充実を図る必要があります。
また、海外展開後の現地スタッフの育成や、本社と海外拠点間のコミュニケーション改善なども重要な課題です。これらの人材関連課題に対して、総合的な支援プログラムの開発と提供を進めていく計画です。
まとめ
日本政策金融公庫の海外展開支援は、中小企業の国際競争力向上と持続的成長を実現するための重要な施策として、着実に発展を続けています。上海、バンコク、ホーチミンの3つの海外駐在員事務所を核とした現地支援体制、充実した融資制度、そして全国の支店網を活用した地域密着型のサポートにより、包括的な海外展開支援を提供しています。
今後は、デジタル化の進展、新興国市場の拡大、サステナビリティへの対応など、新たな課題と機会に対応しながら、支援体制のさらなる充実を図っていく必要があります。日本政策金融公庫は、中小企業の海外展開パートナーとして、時代の変化に対応した革新的な支援サービスを提供し続け、日本経済の国際化と中小企業の成長を支援していくことが期待されています。これらの取り組みを通じて、より多くの中小企業が海外市場で成功を収め、日本経済全体の発展に貢献することが可能となるでしょう。
よくある質問
日本政策金融公庫は中小企業の海外展開にどのように支援しているのですか?
p: 日本政策金融公庫は、海外駐在員事務所の設置を通じて現地情報の提供や相談サービスを強化しています。また、資金調達から現地での事業運営まで、包括的なサポートを提供しています。さらに、海外展開セミナーの開催や個別相談サービスの提供により、企業の海外進出をサポートしています。
日本政策金融公庫の海外展開支援融資制度にはどのような特徴があるのですか?
p: 日本政策金融公庫の海外展開支援融資制度では、最大14億4千万円という大規模な融資限度額を設定しています。また、返済期間は設備資金で最長20年、運転資金で最長7年と企業の投資回収期間を考慮した設定となっています。さらに、EPA/FTA締結国での展開や一定の要件を満たす場合には、特別利率が適用されます。
日本政策金融公庫はどのような地域での支援体制を構築しているのですか?
p: 日本政策金融公庫は、全国各地の支店網を活用して、地域の産業特性や企業ニーズに応じたきめ細かいサポートを提供しています。関東地域や地方都市の支店では、それぞれの地域特性を踏まえた専門的なアドバイスを行っています。また、きらぼしグループとの連携により、地方銀行の地域密着性と政府系金融機関の専門性を組み合わせた支援体制を構築しています。
日本政策金融公庫の海外展開支援にはどのような今後の課題があるのですか?
p: 日本政策金融公庫の海外展開支援では、デジタル化の進展や新興国市場の拡大、サステナビリティへの対応など、新たな機会と課題への対応が求められています。これらの変化に合わせて、支援体制のさらなる充実を図る必要があります。また、人材育成と能力向上も重要な課題であり、総合的な支援プログラムの開発と提供が求められています。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


