税金の支払いは、収入のある国民の義務ですが、予定納税という制度があまり知られていないかもしれません。このブログでは、予定納税の基本的な仕組みから具体的な計算方法、忘れた場合の延滞税についてまで、わかりやすく解説しています。納税に関する理解を深めることで、将来的な経済的なリスクを避けることができるでしょう。
目次
1. 予定納税とは?制度の基本をわかりやすく解説

予定納税とは、特定の所得税納税者が過去の課税実績を基に、毎年の所得税の一部を事前に納付する制度です。この仕組みは、主に高額な所得税を支払う納税者を対象としており、一度の大きな支払いによって生じる経済的な圧力を軽減することを目的としています。
予定納税の目的とメリット
予定納税の主な目標は、税金の支払いの方法を柔軟にし、納税者の財政的な負担を分散させることです。具体的には次のようなメリットがあります:
- 経済的負担の軽減:一度に大きな金額を支払う必要がなくなるため、キャッシュフローに対する負担が軽くなります。
- 計画的な支出:納税額を事前に把握できるため、月々の予算に組み込みやすく、資金計画が立てやすくなります。
- 政府の歳入の安定:税収を適切に回収できることで、政府にとっても安定した収入が確保されます。
予定納税の基本的な仕組み
予定納税のプロセスは、前年の所得税を基に「予定納税基準額」を計算することから始まります。この基準額が一定の金額を超えると、次年度の所得税の一部を前もって納付する必要があります。手続きの流れは以下の通りです:
- 基準額の計算:前年の所得を基に税額が算出され、その金額が予定納税基準額として示されます。
- 通知書の送付:対象となる納税者には、毎年6月中旬頃に税務署から「予定納税額通知書」が届き、支払うべき予定納税額が記載されます。
- 納付手続き:通常、予定納税は7月と11月の2回に分けて基準額の3分の1を納付する形となります。
対象者とは?
予定納税の対象となるのは、前年の納税額が一定の金額(一般的には15万円以上)に達した納税者です。具体的には以下のような方が含まれます:
- 個人事業主
- 副業での収入が高い給与所得者
- 不動産などから一定以上の利益を得ている方
なお、給与所得者でも特別な条件を満たす場合には、予定納税の対象となることもあるため、注意が必要です。
予定納税が適用されると、指定された期日までに必ず納付が求められます。この制度を理解することで、突然の出費に驚かされることなく、計画的に納税を行うことが可能になります。
2. 予定納税の対象者を確認しよう

予定納税は、前年の所得に基づいて所得税の支払額が特定の基準を超えた納税者に適用される制度です。具体的には、前年における所得税の申告額が15万円を上回る納税者が対象となります。このセクションでは、予定納税の対象者がどのようにして確認できるのかについて詳しくご説明します。
対象者の基本条件
予定納税の対象となるためには、次の条件を満たすことが求められます。
- 前年度の納税額が15万円以上であること
- 前年度に確定申告を行い、正確に納税額を記入していること
これによって、前年に高額の税金を払った方は、今年も同様に予定納税が必要になる可能性がありますので、必ずこの点を確認しておくことが重要です。
通知の受け取り
予定納税の対象となる納税者には、毎年6月中旬に税務署から通知書が郵送されます。この通知書には、年ごとの予定納税額およびその納付方法が記載されています。特に、e-Taxを利用している方は、通知がデジタル形式で送信されるため、紙の通知書を受け取りたくない場合は、e-Taxを通じて確認することが非常に重要です。
確認の手段
通知書を受け取ることに加えて、次の方法を用いて自分が予定納税の対象者であるかを確認できます。
- 国税庁のウェブサイト: 所得税に関する予定納税の詳細情報を掲載しており、特定の条件に基づいて確認が可能です。
- 税理士への相談: 所得の複雑さや特例の適用に不安がある場合、専門家に相談することで正確なアドバイスを受けることができ、安心して手続きができます。
注意点
予定納税の対象であることが確認できた場合、お忘れなく納付期限にしっかりと納税を行うことが不可欠です。納付を怠ったり遅れたりすると延滞税が課されるリスクがあるため、特に注意が必要です。納付期限は、原則として7月と11月の二回に分かれている点を覚えておきましょう。
このように、予定納税の対象者をしっかり確認することは、適切な納税を行うために非常に重要です。正しい情報を把握し、適切に対処していくことが求められます。
3. 納付時期と具体的な金額の計算方法
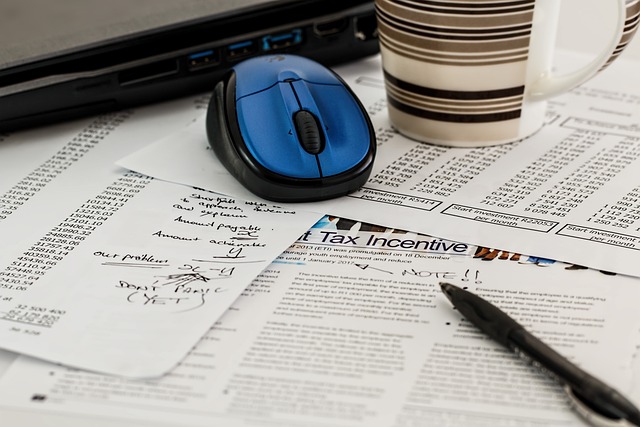
予定納税は、前年の所得税額が一定の基準を超える場合に行われる先払いの税金です。ここでは、その納付時期と具体的な金額の計算方法について詳しく見ていきます。
納付時期
予定納税の納付は、原則として以下の2回に分かれています。
- 第1期分: 毎年7月中の指定された期間内
- 第2期分: 毎年11月中の指定された期間内
これらの納付時期を適切に把握し、忘れずに納付することが重要です。具体的には、令和6年の場合、以下の日程で納付が行われます。
- 第1期分: 令和6年7月1日から同年9月30日まで
- 第2期分: 令和6年11月1日から同年12月2日まで
金額の計算方法
予定納税額は、前年の確定申告で算出された所得税額を基に計算されます。次のステップで金額を求めます。
-
前年の所得税額を確認する
確定申告書に記載された前年の納税額をチェックします。 -
金額を3等分する
確定した所得税額を3で割ります。この金額が、各期に支払う予定納税額となります。
例えば、前年の所得税額が45万円の場合:
– 第1期分: 15万円
– 第2期分: 15万円
- 特別控除を考慮する
令和6年分の予定納税額には、予定納税特別控除(本人分3万円)が適用されるため、第1期分の計算ではこの特別控除を差し引く必要があります。
具体例
例えば、前年の所得税額が30万円であった場合、計算方法は次のようになります。
- 第1期分:
- 計算式: (30万円 × 1/3) – 3万円(特別控除)
-
支払額: 7万円
-
第2期分:
- 計算式: 30万円 × 1/3
- 支払額: 10万円
これらの金額を、指定された納付期限内に納める必要があります。計算誤りや支払期限を忘れると、延滞税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
4. 予定納税を忘れるとどうなる?延滞税について

予定納税を指定された期限内に納付しないと、延滞税という追加の税負担が生じます。この延滞税は、支払いが遅れた日数によって異なり、納付が遅れるほど金額が増加するため、注意が必要です。税金関連の規定をしっかりと理解することは、納税者にとって非常に大切です。
延滞税の計算方法
延滞税は、次の基準に基づいて算出されます。具体的には、納期限の翌日からの遅延日数によって異なる金利が適用されます。
-
納期限の翌日から2ヶ月まで
– 年率「7.3%」または「延滞税特例基準割合+1.0%」のいずれか低い方が用いられます。
– 令和5年の場合、2ヶ月以内の延滞税率は年2.4%です。 -
納期限の翌日から2ヶ月以降
– 年率「14.6%」または「延滞税特例基準割合+7.3%」の低い方が適用されます。
– 令和5年の期間の場合、2ヶ月を超えた延滞税率は年8.7%となります。
たとえば、50万円の税金を延滞した場合、30日間の計算は次のようになります。
- 50万円 × 年率7.3% × 30日 ÷ 365日 = 3,000円
このように、元の税額に加えて延滞税が発生し、無視できない金額になることがあるので注意が必要です。
延滞税の影響
予定納税を忘れると、以下のような影響が考えられます:
- 金銭的な負担の増加: 延滞税が発生することで、本来支払うべき税金以上の負担が生じる可能性があります。
- 納税計画の不安定さ: 繰り返し延滞があると、今後の納税設計に影響を及ぼす不安定さが増すことがあります。
どのように対処するか?
延滞税を回避するためには、以下の対策が有効です:
- 納税スケジュールを管理: カレンダーやスマートフォンのアプリを使って納付期限を設定し、リマインダー機能を活用しましょう。
- 金融状況の定期的なチェック: 自身の支払い能力を定期的に評価し、必要であれば減額申請を検討することも助けになります。
- 早めの納付: 期限が近づいている場合は、早めに納めることで延滞税のリスクを軽減することが可能です。
このように、予定納税を忘れないように計画的な管理と迅速な対応が必要です。延滞税を避けて、金銭的な負担を軽減するための準備をしっかりと進めましょう。
5. 所得が減った場合の減額申請の方法

所得税の予定納税は、前年の所得を元に計算されます。しかし、思いがけない事情、例えば病気による入院や経済的な困難、あるいは事業を停止せざるを得ない状況に陥った際に、所得が減少することもあります。このような状況に対処するためには、予定納税の減額申請を行うことが大変重要です。ここでは、具体的な手続きについて詳しく解説します。
減額申請の対象者
予定納税の減額申請が認められる方には、以下のような条件があります。
- 事業の廃業、休業、または失業があった場合
- 前年と比較して明らかに所得が低下する予測がある場合
- 災害や盗難などにより事業資産が損害を受けた場合
- 控除額の増加により、前年よりも納税額が減少する見込みがある場合
減額申請の手続き
減額申請を進めるにあたっては、以下のステップを踏んで必要書類を整え、税務署に提出する必要があります。
-
減額申請書の取得
税務署または国税庁の公式ウェブサイトから、適切な減額申請書をダウンロードします。 -
必要事項の記入
減額を要する理由、前年の所得税の金額、今年度の見込み所得などを詳細に記入します。また、できる限り減収を証明する書類を添付することが推奨されます。 -
申請書の提出
記入済みの申請書を、担当の税務署へ持参または郵送します。この時、所得計算の根拠となる資料も同封すると良いでしょう。
提出期限
減額申請には厳密な提出期限が設定されています。令和5年度の場合、以下のようになります。
- 第1期分および第2期分の両方を申請する場合:その年の7月15日
- 第2期分だけの申請の場合:その年の11月15日
期日を過ぎてしまうと申請が受け付けられなくなるため、注意が必要です。
減額が承認されると
申請が認められたかどうかは、税務署から通知されます。この結果は「承認」「一部承認」「却下」のいずれかになります。特に却下となった場合、予定納税額の減少は行えませんので、結果は必ず確認しておくことが重要です。
このように、所得が減少した場合には、適切な手続きを経て納税額を見直すことが可能です。迅速な行動が、リスクを軽減する第一歩となります。
まとめ
予定納税は、高額納税者のために設けられた制度で、一度の大きな支払いを分散させて、納税者の経済的負担を軽減することが目的です。この制度の仕組みを理解し、適切に利用することで、計画的な税金支払いが可能になります。また、予期せぬ状況で所得が減少した場合には、減額申請を行うことで、柔軟に対応することもできます。予定納税をしっかりと把握し、期限に忘れずに納付することが重要です。そうすれば、無駄な延滞税を避けながら、自身の財務管理を安定させることができるでしょう。
よくある質問
予定納税とはどのようなものですか?
予定納税とは、前年度の所得税額が一定金額以上の納税者に対し、当年度の所得税の一部を事前に納付する制度です。この仕組みは、大額の所得税を支払う納税者の経済的負担を軽減することを目的としています。
予定納税の対象者はどのように確認できますか?
前年度の所得税申告額が15万円を超えた納税者が予定納税の対象となります。税務署から6月中旬に通知書が送付されるほか、国税庁のウェブサイトや税理士に相談することで、自身が対象者かどうかを確認できます。
予定納税の具体的な納付方法と金額の計算方法は?
予定納税は通常7月と11月の2回に分けて納付し、その金額は前年度の所得税額を3等分した額となります。ただし、本人分の特別控除3万円が第1期分から差し引かれます。
予定納税を忘れると延滞税が発生するリスクがあるのですか?
はい、予定納税の期限内に納付しないと、納期限の翌日から2ヶ月以内は年2.4%、2ヶ月を超えると年8.7%の延滞税が課されます。このため、納付期限の管理や早期の納付が重要です。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


