予定納税は個人事業主やフリーランスの方にとって避けられない重要な税務手続きですが、そのルールやシステムについて良く理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。そこで本ブログでは、予定納税の仕組みから対象者の見分け方、納付時期と金額の計算方法、さらには支払い方法や減額申請のポイントまで、予定納税に関する幅広い情報を分かりやすく解説していきます。個人事業主の方はもちろん、副業をされている方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひご一読ください。
目次
1. 予定納税とは?初心者でもわかる基本の仕組み

予定納税とは、特定の基準をクリアした納税者が、前年度の利益に基づき、必要な所得税を事前に支払う仕組みです。この制度は、納税者の経済的な負担を和らげるとともに、税務署が計画的かつ効率的に税金を徴収できるように設計されています。
予定納税の基本的な流れ
-
前年の所得税額に基づく判断
予定納税が発生するのは、前年の所得税の納付が15万円以上であった納税者です。この条件を満たす方は、翌年においても予定納税を行う必要があります。 -
納付のタイミング
予定納税は年に2回行われます。具体的には以下の時期で分割して納付します:
– 第1期分:7月中
– 第2期分:11月中 -
税額の計算
予定納税の金額は、前年の納税額に基づいて算出されます。通常は前年の納税額の3分の1が、各期の納付額に相当します。ただし、前年の収入の状況や特別措置によって、金額に変動が生じることがありますので、正確な計算が重要です。
予定納税のメリット
予定納税の仕組みは、税務署と納税者の双方に多くのメリットをもたらします。
-
納税者の負担軽減
一度に多額の税金を支払うことを避け、分割で納付することで、資金繰りの負担が軽くなります。 -
計画的な税金回収
税務署にとっては、予定納税によって安定した税収が見込め、税収の予測が容易になり、国の財政運営に貢献します。
誰が対象となるのか?
予定納税の対象は、以下の条件を満たす個人事業主やフリーランスの方々です:
- 前年の納税額が15万円以上であること
- 所得が複数あり、給与以外の副収入があること
これらの条件を満たしている場合、翌年度に予定納税が必要となる可能性があるため、しっかりと確認しておくことをお勧めします。
予定納税は、確定申告の前に税金を納めるための重要なシステムであり、特に個人事業主にとっては資金計画の一環として、前もって対策を講じることが不可欠です。
2. 予定納税の対象者をチェック!15万円基準と確認方法

予定納税の対象者は、前年に支払った所得税が15万円を超える納税者です。この基準は、前年の確定申告をもとに決定されるため、自分自身の納税状況をしっかり把握することが大切です。ここでは、予定納税の対象者について詳しく見ていきましょう。
予定納税の基準
予定納税は前年に支払った所得税が15万円以上の納税者に適用されます。この基準をクリアしているかどうかは、次の要素を参考にして確認できます。
- 前年の確定申告の結果: 確定申告で報告した所得税額が15万円を超えている場合、予定納税の対象となります。
- 給与所得者と副業の状況: 一般的に給与所得者は勤務先での源泉徴収により、予定納税の対象とはならないことが多いですが、副業収入が多い場合はそれに注意が必要です。
通知書の確認方法
毎年6月中旬に、税務署から「所得税及び復興特別所得税の予定納税額通知書」が郵送されます。この通知書が届くと、予定納税を行う義務が出てくるため、内容を確認し、予定納税額や納付期限をしっかり把握しておくことが重要です。
予定納税の確認手順
- 前年の納税額をしっかり確認: まずは昨年の確定申告での所得税額が15万円を超えているかどうかを確認しましょう。
- 通知書の受領確認: 税務署からの通知書が毎年6月中旬に届くので、その内容に基づいて予定納税が必要かを判断します。
- 問い合わせを忘れずに: 計算ミスや通知書が届かない場合は、すぐに税務署に連絡して確認してください。特に副収入のある方は、自分の状況に合った対処が求められます。
注意すべきポイント
- 通知書は必ず確認すること: 税金の支払いを怠ると延滞税が課される可能性があるため、通知書が届いた際には必ず確認し、予定納税を行うことを心がけましょう。
- 個人事業主も注意が必要: 予定納税は法人法人だけでなく、個人事業主にも該当します。前年に15万円以上の納税実績がある方は特に気を付ける必要があります。
予定納税の対象者となった場合には、適切な手続きを行い、税務署からの通知書を見逃さないように注意を払いましょう。自身の納税状況をしっかりと把握することで、スムーズな納税を実現できます。
3. 納付時期と金額の計算方法をわかりやすく解説
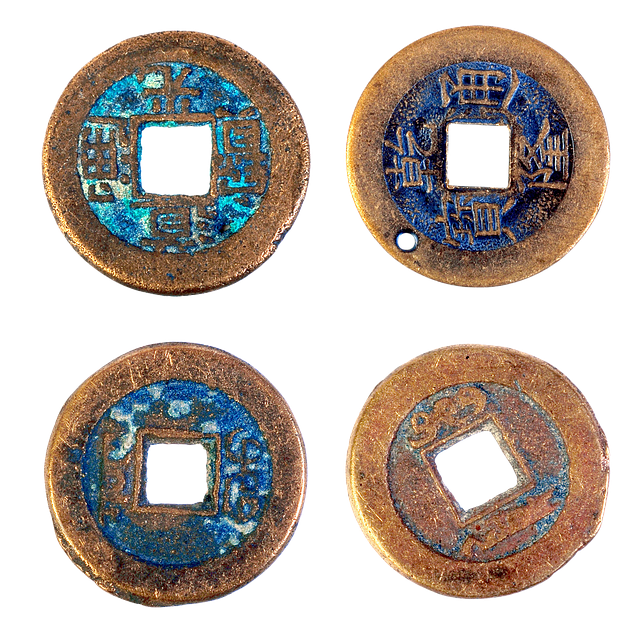
予定納税は前年の納税額をもとに計算されるため、その金額を正確に把握することが重要です。特に、予定納税額はその年の納税義務を果たすための目安として機能します。以下では、納付時期と金額の計算方法について詳しく解説します。
納付時期
予定納税は、原則として年に2回に分けて行われます。具体的な納付期間は以下の通りです。
- 第1期分:毎年7月から9月末まで
- 第2期分:毎年11月から12月初めまで
各期の納期限は厳守する必要があります。延滞すると延滞税が発生するため、早めに準備しておくことをおすすめします。
予定納税額の計算方法
予定納税額は前年の確定申告での納税額を基にして計算されます。以下がその計算プロセスです。
-
前年の納税額を確認:
– 昨年の確定申告書を参照し、そこで求められた所得税額を確認します。 -
金額を3で割る:
– 確定した納税額を3で割り、その結果がそれぞれの予定納税額となります。たとえば、前年の所得税が45万円であった場合、予定納税額は15万円となります。 -
特別控除の適用:
– 令和6年からは特別控除が適用されるケースもあります。この場合、第1期分の予定納税額は、基準額から30,000円を差し引いて計算します。
具体的な例を挙げると、以下のようになります。
計算例
- 昨年の所得税額が45万円だった場合:
- 第1期納付額 = 45万円 ÷ 3 = 15万円
- 第2期納付額も同様に15万円
- もし特別控除が適用されると、実際の第1期分の支払額は 15万円 – 3万円 = 12万円となります。
注意点
- 納期限の厳守:納期限を過ぎると延滞税が課されるため、きちんと納付スケジュールを管理しましょう。
- 減額申請の検討:前年と比べて所得が大幅に減少した場合には、減額申請が認められることがあります。早めに税務署に相談すると良いでしょう。
このように、予定納税の納付時期と金額の計算は明確で、事前に準備しておくことで、無駄なトラブルを避けることができます。自分自身の所得状況を定期的に確認し、必要な手続きを行うことが大切です。
4. 知って得する予定納税の5つの支払い方法

予定納税を行う際には、多様な支払い方法が用意されており、それぞれの納税者のライフスタイルやニーズに応じて選択することが可能です。ここでは、知っておくと役立つ5つの支払い手段について詳しくご紹介します。
ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
ダイレクト納付は、納税者の銀行口座から自動で引き落としが行われる便利な方法です。事前に「ダイレクト納付利用届出書」を提出しておく必要がありますが、この仕組みを利用することで納税を忘れてしまうリスクを大幅に軽減できます。さらに、指定した日時に合わせて即時引き落としを行えるため、計画的な納税が非常に簡単になります。
クレジットカード納付
クレジットカードを用いた納付方法は、オンラインで簡単に手続きができるため非常に人気があります。手数料がかかる場合がありますが、ポイントが貯まることも多く、クレジットカード利用者には魅力的な選択肢です。国税クレジットカードお支払いサイトにアクセスし、必要事項を入力することでスムーズに納税処理を行うことが可能です。
コンビニ納付(QRコード、バーコード)
指定のコンビニエンスストアでの納付は、さらに手軽な方法です。国税庁のウェブサイトでQRコードを生成し、それを印刷して持参することで納税が簡単にできます。また、日常の買い物と一緒に支払いができるので、時間を有効活用したい方にはぴったりです。しかし、納付金額には最大30万円という制限があるため、計画を立てる際には注意が必要です。
金融機関や税務署での直接納付
現金で納付したい方には、金融機関や税務署で直接納付する方法が適しています。納付書を持参して窓口で手続きを行うことになります。この方法の利点は、特に金額に制限が無いため、必要に応じて領収書を確認しながら安心して納税できる点です。ただし、窓口の営業時間に合わせる必要があるため、事前に確認しておくことが大切です。
電子納付(e-Tax)
電子納付はPCやスマートフォンを使った方法で、e-Taxの利用が求められます。事前に利用登録をする必要がありますが、納税手続きは非常にスムーズです。また、特定の金融機関を通じて「ペイジー」を活用することで、さらに便利に納付することができます。利便性を重視する納税者には特におすすめの手段です。
このように、予定納税には多彩な支払い方法があります。それぞれのライフスタイルやニーズに応じて最適な方法を選ぶことで、納税の負担を軽減し、有効に時間を活用できるでしょう。
5. 所得が減った時の救済制度!減額申請のポイント

所得が減少すると、年間の予定納税額が過剰に設定されることがあります。このような事態に対処するため、税務署では減額申請制度を導入しており、納税者が自己の状況を反映させ、実際の税負担を軽減できるように支援しています。ここでは、この制度の利点や対象者、手続き方法について詳しく解説していきます。
減額申請の対象者
減額申請を行うことができるのは、次のような状況にある方々です:
- 廃業や臨時休業を強いられた場合
- 昨年に比べて明らかな所得減少が見込まれる方
- 自然災害や盗難、詐欺によって事業資産に被害を受到けた方
- 所得控除や税額控除が増加し、実際の所得税が減少する見込みのある方
これらの条件に該当する方は、ぜひ税務署での相談を行い、減額申請を検討することをお勧めします。
減額申請の手続き方法
減額申請を進めるには、次のステップが必要です:
-
申請書の作成
減額申請書を国税庁の公式ウェブサイトからダウンロードし、必要事項を的確に記入します。前年の所得税額や今年度の見込み所得、具体的な減額理由を記載することが重要です。 -
必要書類の準備
所得の減少を証明するための資料(例:損益計算書や確定申告書など)を整え、申請書に添付します。これにより、申請の信頼性が向上します。 -
書類の提出
完成した申請書を所轄の税務署に提出します。提出方法は、e-Taxを利用するか、郵送または直接持参することが可能です。 -
審査結果の確認
書類を提出した後、税務署から「承認」または「却下」の通知が届きます。この結果を忘れずに確認し、もし承認されなかった場合は予定納税額の支払いが求められます。
減額申請の期限
減額申請には厳しい期限が設定されています。2024年の減額申請に関連する具体的な期限は次の通りです:
- 第1期と第2期を同時に申請する場合:7月31日
- 第2期のみの申請の場合:11月15日
これらの期限を超えてしまうと、減額が承認されなくなるため、しっかりとスケジュールを管理することが重要です。
減額申請をする際の注意点
申請を進める際に注意が必要なポイントは以下の通りです:
- 前年との比較の検討:前年の所得と比較し、減額理由が適切であることを必ず確認しましょう。
- 還付金に関する認識:申請せず予定納税を支払った場合、確定申告での還付を受けられる可能性があることを忘れないでください。
- 手続きの複雑性:手続きが難解になることもあるため、税理士や専門家に相談することも一つの有効な手段です。
所得が減少した際には、適切に減額申請を行うことが非常に重要です。この手続きを通じて税負担を軽減し、資金繰りを円滑にすることが可能になります。
まとめ
予定納税は事業者にとって重要な制度ですが、状況に応じて柔軟に対応する必要があります。所得が減少した場合は減額申請を活用し、確定申告では還付金の請求も検討しましょう。一方で、正しい納付時期と金額を把握し、スムーズな納税を心がけることも大切です。税制の理解を深め、自身に最適な支払い方法を選択することで、効率的な資金管理と税負担の軽減を実現できるでしょう。
よくある質問
予定納税とはどのようなものですか?
予定納税とは、前年度の所得税額に基づき、翌年度の所得税の一部を事前に納付する制度です。この仕組みにより、納税者の経済的な負担を和らげるとともに、税務署が計画的かつ効率的に税金を徴収できるようになります。
誰が予定納税の対象となるのですか?
予定納税の対象は、前年の所得税額が15万円を超える個人事業主やフリーランスの方です。この基準をクリアしていれば、翌年度に予定納税を行う必要があります。
予定納税の支払い方法にはどのようなものがありますか?
予定納税の支払い方法には、ダイレクト納付、クレジットカード納付、コンビニ納付、金融機関や税務署での直接納付、電子納付(e-Tax)など、様々な選択肢があります。納税者のライフスタイルやニーズに合わせて、最適な方法を選択することができます。
所得が減少した場合はどのような対応ができますか?
所得が減少した場合は、減額申請制度を利用することで、実際の税負担を軽減することができます。申請書の作成や必要書類の準備、期限内の提出が重要となります。申請が承認されれば、予定納税額を減額することが可能です。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


