目次
はじめに
「経営を立て直したいのに銀行から融資を断られてしまった。この先どうすればいいのだろう。」多くの経営者や個人事業主がこのような悩みを抱えています。事業資金が借りられないという問題は、企業の成長や事業継続にとって深刻な課題となります。
しかし、一度や二度融資を断られても、まだ希望はあります。融資を断られた理由を正しく把握し、適切な対策を講じることで、資金調達の可能性は大きく高まります。本記事では、事業資金を借りられない原因から具体的な対処法まで、包括的に解説していきます。
事業資金を借りられない主な原因
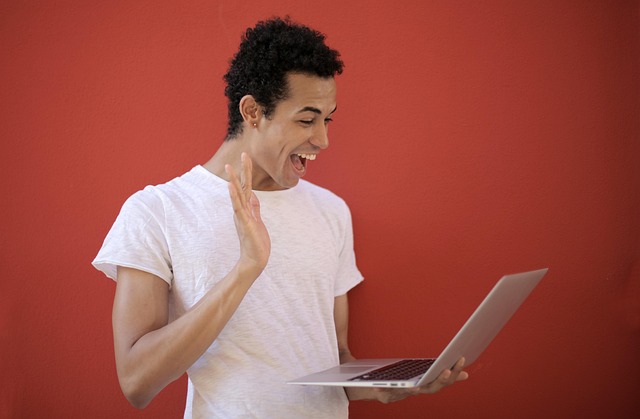
融資を受けられない背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。まずは自社がどの問題に該当するかを正確に把握することが、解決への第一歩となります。ここでは、最も一般的な原因について詳しく見ていきましょう。
信用情報と返済履歴の問題
金融機関が最も重視するのが信用情報です。過去にクレジットカードや既存の借入金の返済に遅延がある場合、それが信用情報機関に記録され、新たな融資審査に大きく影響します。特に3ヶ月以上の延滞や債務整理の履歴がある場合、「金融ブラック」と呼ばれる状態になり、通常の銀行融資は極めて困難になります。
また、税金や社会保険料の滞納も融資審査で必ずチェックされる項目です。これらの公的債務の未払いは、事業の信頼性そのものを疑問視される要因となります。滞納がある場合は、融資申請前に必ず清算するか、分割払いの手続きを完了させておく必要があります。
自己資金不足の問題
多くの金融機関では、融資額に対する自己資金の割合を重要な審査基準としています。一般的に、創業時の場合は総投資額の3分の1以上、既存事業の場合でも10%以上の自己資金が求められることが多いです。自己資金が不足していると、経営者の本気度や事業への覚悟が疑問視され、融資が困難になります。
自己資金として認められるのは、基本的に預貯金や有価証券などの流動性の高い資産です。ただし、親族からの贈与金についても、適切な手続きを踏んでいれば自己資金として扱われる場合があります。重要なのは、これらの資金の出所を明確に説明できることです。
事業計画書の不備
融資審査において事業計画書は極めて重要な役割を果たします。計画書が曖昧で具体性に欠けていたり、数値の根拠が不明確だったりすると、融資担当者は事業の実現可能性を判断できません。特に売上予測が楽観的すぎる場合や、競合分析が不十分な場合は、計画の信頼性が疑われます。
優れた事業計画書には、市場分析、競合状況、販売戦略、財務計画などが論理的に組み立てられており、読み手が事業の将来性を具体的にイメージできるような内容が求められます。また、リスク要因とその対策についても明記することで、経営者のリスク管理能力をアピールできます。
決算書の数字が良くない
既存事業者の場合、過去3年程度の決算書は融資審査の核心的な判断材料となります。連続して赤字を計上していたり、債務超過の状態が続いていたりすると、返済能力に疑問を持たれ、融資は困難になります。また、売上の急激な減少や利益率の悪化なども、事業の将来性に対する不安要素として評価されます。
決算書で特に注目されるのは、売上高、営業利益、自己資本比率、流動比率などの指標です。これらの数字が業界平均を大きく下回っている場合は、融資申請前に改善策を検討するか、数字が悪化した理由を明確に説明できるよう準備しておく必要があります。
融資を断られた際の対処法

融資を断られても、そこで諦める必要はありません。適切な対処法を実践することで、状況を改善し、再度融資を受けられる可能性を高めることができます。ここでは、段階的なアプローチ方法を詳しく解説します。
断られた理由の詳細な把握
まず最初にすべきことは、金融機関に断られた具体的な理由を聞き出すことです。多くの場合、金融機関は詳細な理由を積極的には教えてくれませんが、丁寧にお願いすることで、ある程度の情報は得られることが多いです。「今後の改善のために」という姿勢で質問すると、担当者も協力してくれる可能性が高まります。
理由が判明したら、それが短期間で改善可能なものか、中長期的な取り組みが必要なものかを分類します。例えば、必要書類の不備や事業計画書の内容不足などは比較的短期間で対応できますが、決算内容の改善や信用情報の回復には時間がかかります。この分類に基づいて、今後の戦略を立てることが重要です。
問題点の具体的な改善策
特定された問題点に対しては、具体的かつ実効性のある改善策を実行する必要があります。自己資金不足の場合は、個人の預貯金を増やしたり、親族からの資金援助を検討したりします。事業計画書に問題がある場合は、市場調査を充実させ、より現実的な数値予測を行い、専門家のアドバイスを受けて内容を改善します。
信用情報に問題がある場合は、まず現在の状況を信用情報機関で確認し、可能な限り問題を解決します。延滞がある場合は速やかに清算し、分割払いが可能なものは正式な手続きを行います。これらの改善には時間がかかる場合もありますが、着実に実行することで、次回の融資審査での評価向上につながります。
専門家との連携
融資に関する問題の解決には、税理士や中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家との連携が非常に有効です。特に認定経営革新等支援機関の資格を持つ専門家は、融資支援に関する豊富な経験と知識を持っており、審査に通りやすい事業計画書の作成支援や、適切な金融機関の選定についてアドバイスを受けることができます。
専門家を活用する最大のメリットは、客観的な視点から事業を分析してもらえることです。経営者自身では気づかない問題点や改善ポイントを指摘してもらえるほか、金融機関との交渉においても専門的なサポートを受けることができます。費用はかかりますが、融資成功の可能性を大幅に高めることができる投資と考えるべきでしょう。
代替的な資金調達方法

銀行融資が困難な場合でも、事業資金を調達する方法は他にもあります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、事業の状況や緊急度に応じて最適な選択肢を検討することが重要です。
日本政策金融公庫の活用
日本政策金融公庫は、民間金融機関よりも柔軟な審査基準を持つ政府系金融機関です。創業支援や中小企業支援を主要な目的としているため、銀行で融資を断られた企業でも借り入れできる可能性があります。特に新規事業や革新的な取り組みに対しては、将来性を重視した審査が行われるため、決算内容に不安がある企業にとっても有力な選択肢となります。
日本政策金融公庫の融資制度は多岐にわたり、無担保・無保証人の制度も用意されています。金利も比較的低く設定されており、長期間での返済が可能な場合が多いため、事業の負担を軽減できます。ただし、審査には一定の時間がかかるため、急ぎの資金需要には対応が困難な場合もあります。
地方銀行・信用金庫への相談
地方銀行や信用金庫は、地域密着型の金融機関として、大手銀行とは異なる審査基準を持っている場合があります。特に地元の事業者に対しては、事業の実態を理解した上で柔軟な対応をしてくれることが多く、大手銀行で断られた企業でも融資を受けられる可能性があります。また、地域の経済発展を支援するという使命もあるため、地元企業への融資に積極的な姿勢を示すことが多いです。
これらの金融機関では、決算書の数字だけでなく、経営者の人柄や事業への取り組み姿勢、地域への貢献度なども評価要因として考慮されます。そのため、数字上では問題があっても、事業の将来性や社会的意義をしっかりとアピールできれば、融資を受けられる可能性があります。普段取引のない金融機関でも、経営革新計画の承認や詳細な事業計画を提示することで、借入金返済の確実性をアピールできます。
ノンバンクからの借入
ノンバンクとは、銀行以外の金融業者のことで、消費者金融大手のアイフルやレイクなども事業者向けの融資を行っています。ノンバンクの最大の特徴は、審査が銀行よりも緩やかで、申し込みから資金調達までの期間が短いことです。通常は1週間以内で結果が出るため、緊急の資金需要に対応できます。
また、必要書類も銀行より少なく、試算表や資金繰り表などの詳細な財務資料を求められないことが多いです。これにより、銀行では融資を受けられない企業でも資金調達が可能になります。ただし、金利は銀行融資よりも高く設定されているため、短期間での利用や緊急時の資金調達手段として考えるのが適切でしょう。
補助金・助成金の活用
補助金や助成金は、返済義務のない資金調達手段として非常に魅力的な選択肢です。IT導入補助金、ものづくり補助金、キャリアアップ助成金など、中小企業や個人事業主向けの制度が数多く用意されています。これらの制度は信用情報の照会がないため、金融ブラック状態の企業でも活用できます。
補助金・助成金の申請には、事業計画書や申請書類の作成が必要ですが、融資とは異なり返済の必要がないため、事業の財務負担を大幅に軽減できます。ただし、支給要件や申請タイミングによって支給額が変わるため、最新情報を定期的に確認し、計画的に申請することが重要です。専門家のサポートを受けることで、採択率を高めることも可能です。
個人事業主特有の対策

個人事業主は法人と比較して、融資審査においてより厳しい基準が適用されることが多いです。しかし、個人事業主ならではの特徴を活かした資金調達方法も存在します。ここでは、個人事業主が知っておくべき特別な対策について解説します。
個人事業主が利用しやすい金融機関
個人事業主にとって最も利用しやすいのは、日本政策金融公庫です。創業支援に力を入れており、担保や保証人不要の制度も用意されているため、開業したばかりの個人事業主でも融資を受けられる可能性があります。低金利の融資制度が豊富で、事業の将来性を重視した審査を行うため、実績が少なくても事業計画がしっかりしていれば融資を受けられます。
地域の信用金庫も個人事業主にとって有力な選択肢です。地域密着型の特性を活かし、事業の実態を理解した上で融資判断をしてくれます。大手銀行では画一的な審査基準が適用されがちですが、信用金庫では個別の事情を考慮した柔軟な対応が期待できます。普段からの取引関係を構築しておくことで、いざという時の資金調達がスムーズになります。
ビジネスローンの活用
個人事業主が迅速に資金調達したい場合、ビジネスローンは有効な選択肢となります。審査が柔軟で融資スピードが早く、創業間もない事業主でも借りやすいという特徴があります。手続きも簡単で、インターネット上で申し込みから契約まで完結できる場合も多く、忙しい個人事業主にとって利便性の高いサービスです。
ただし、ビジネスローンは金利が高めに設定されているため、長期間の利用には注意が必要です。運転資金の一時的な補填や、売上入金までのつなぎ資金として活用するのが適切でしょう。利用前には必ず返済計画を立て、無理のない範囲での借入を心がけることが重要です。
ファクタリングサービス
ファクタリングは、売掛金を金融機関やファクタリング会社に売却することで、即座に現金化できるサービスです。融資ではないため、信用情報に問題があっても利用でき、審査も売掛先の信用力が重視されるため、自社の財務状況が良くなくても資金調達が可能です。特に請求書決済を行っている個人事業主にとっては、非常に有効な資金調達手段となります。
ファクタリングの最大のメリットは、最短即日で資金調達が可能なことです。緊急の支払いや設備投資の機会を逃したくない場合には、非常に有効な選択肢となります。ただし、手数料が比較的高く、取引先に知られる可能性があるなどのデメリットもあるため、利用前には十分な検討が必要です。
制度融資と政府支援策

民間金融機関からの融資が困難な場合でも、国や地方自治体が提供する各種制度を活用することで、事業資金を調達できる可能性があります。これらの制度は、中小企業や個人事業主の事業継続と成長を支援することを目的としており、通常の融資よりも有利な条件が設定されています。
地方自治体の制度融資
地方自治体の制度融資は、自治体、金融機関、信用保証協会の三者が連携して提供する融資制度です。自治体が利子補給を行い、信用保証協会が保証を提供することで、通常よりも低い金利で融資を受けることができます。各自治体によって制度の内容は異なりますが、創業支援、経営安定化、事業拡大など、様々な目的に応じた制度が用意されています。
制度融資の申し込みは、通常、指定された金融機関を通じて行います。審査は金融機関と信用保証協会の両方で行われますが、自治体の支援があるため、通常の融資よりも審査に通りやすい傾向があります。ただし、申し込みから実行までに時間がかかる場合が多いため、資金需要の時期を考慮して早めに準備することが重要です。
経営革新計画の活用
経営革新計画は、中小企業が新商品の開発や新サービスの提供など、経営の向上を図る計画について、都道府県知事の承認を受ける制度です。承認を受けると、政府系金融機関からの低利融資、信用保証協会の特別保証枠の拡大、税制上の優遇措置など、様々な支援策を受けることができます。
経営革新計画の承認を得るためには、新規性、独自性、市場性、実現可能性などの要件を満たす必要があります。計画書の作成には専門知識が必要なため、中小企業診断士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。承認を受けた企業は、その後の融資審査においても高く評価される傾向があり、資金調達の可能性が大幅に向上します。
セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度は、経済環境の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金調達を支援する制度です。業況の悪化している業種に属する事業者や、取引先の倒産により影響を受けた事業者などが対象となり、通常の保証とは別枠で信用保証協会の保証を受けることができます。
この制度を利用するためには、市区町村長の認定が必要ですが、要件を満たしていれば比較的容易に認定を受けることができます。保証料率も通常より優遇されており、資金繰りに困っている企業にとって非常に有効な支援策となります。制度の詳細や対象業種については定期的に見直されているため、最新の情報を確認することが重要です。
まとめ
事業資金を借りられないという問題は、多くの経営者が直面する深刻な課題ですが、決して解決不可能な問題ではありません。重要なのは、融資を断られた原因を正確に把握し、それに対する適切な対策を講じることです。信用情報の改善、自己資金の確保、事業計画書の充実など、基本的な要素をしっかりと整備することで、融資の可能性は大幅に向上します。
また、銀行融資以外にも様々な資金調達手段が存在することを理解し、自社の状況に最適な方法を選択することが重要です。日本政策金融公庫、地方銀行、信用金庫、ノンバンク、補助金・助成金など、それぞれに特徴と適用条件があります。専門家との連携を通じて、これらの選択肢を効果的に活用することで、事業資金の調達は必ず実現できるでしょう。
よくある質問
銀行から融資を断られた場合、どうすればよいですか?
まず、なぜ融資を断られたのかを金融機関に確認し、その問題点を改善するための具体的な対策を実行することが重要です。また、日本政策金融公庫やノンバンクなど、銀行以外の融資選択肢を検討することで、資金調達の可能性を高めることができます。専門家のサポートを受けて、自社に合った最適な方法を見つけることが成功への近道です。
個人事業主として融資を受けるにはどうすればよいですか?
個人事業主にとって有利な選択肢は、日本政策金融公庫や地域の信用金庫です。これらの金融機関は、個人事業主の事情を理解した上で融資審査を行うため、大手銀行と比べて融資を受けやすい傾向にあります。また、ビジネスローンやファクタリングなども、迅速な資金調達に活用できる方法です。ただし、返済計画を十分に検討し、無理のない範囲での借入を心がけることが重要です。
事業計画書の作成で注意すべきことはありますか?
事業計画書は融資審査において極めて重要な役割を果たします。計画書には、市場分析、競合分析、販売戦略、財務計画などが論理的に組み立てられている必要があります。特に、売上予測や数値目標は現実性のあるものにする必要があり、根拠を明確に示すことが求められます。また、リスク要因とその対策についても記載することで、経営者の問題解決能力を示すことができます。専門家のサポートを得て、審査に通りやすい計画書を作成することが重要です。
補助金や助成金を活用するにはどうすればよいですか?
補助金や助成金は、返済義務のない資金調達手段として非常に魅力的です。IT導入補助金やものづくり補助金など、中小企業や個人事業主向けの制度が数多く用意されています。これらの制度は信用情報の照会がないため、金融ブラック状態の企業でも活用できます。ただし、支給要件や申請タイミングによって支給額が変わるため、最新情報を定期的に確認し、計画的に申請することが重要です。専門家のサポートを受けることで、採択率を高めることも可能です。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


