目次
はじめに
年末調整における扶養控除は、納税者の経済的負担を軽減する重要な制度です。16歳以上の扶養親族がいる場合、一定の要件を満たすことで所得税や住民税の軽減を受けることができます。この制度は、家族を扶養している納税者にとって大きなメリットとなりますが、適用要件や控除額、申告方法を正しく理解することが重要です。
特に令和7年度税制改正により、扶養控除に関する制度が大幅に見直されています。年収の上限額が引き上げられるほか、新たな控除制度も導入される予定です。これらの変更点を適切に理解し、年末調整の手続きを正確に行うことで、最大限の税制メリットを享受することができるでしょう。
扶養控除制度の基本概念
扶養控除は、所得税法に基づいて「扶養親族」を持つ納税者が受けられる所得控除制度です。この制度により、総所得金額から一定額を差し引くことができ、結果として所得税や住民税の負担を軽減することができます。扶養控除を受けるためには、扶養親族が特定の要件を満たしている必要があり、その要件は年末時点での状況に基づいて判定されます。
この控除制度は、家族の経済的支援を行っている納税者に配慮した社会保障的な側面を持っています。子育て世代や高齢者を扶養している世帯にとって、税負担の軽減は家計の安定に直結する重要な要素となります。また、社会全体としても、家族間の支え合いを税制面で後押しする効果があります。
対象となる扶養親族の範囲
扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」は、12月31日時点で16歳以上であることが基本要件となります。この年齢制限は、義務教育期間中の子どもに対する児童手当などの他の支援制度との重複を避けるために設けられています。対象となる親族の範囲は、配偶者以外の直系血族および兄弟姉妹、さらには一定の親族関係にある者まで含まれます。
重要なポイントとして、扶養親族は納税者と「生計を一にする」必要があります。これは必ずしも同居を意味するものではなく、経済的な支援関係があることを指します。例えば、大学生の子どもが一人暮らしをしていても、親が学費や生活費を負担している場合は生計を一にしていると判断されます。このような柔軟な解釈により、現代の多様な家族形態に対応しています。
年末調整での申告手続き
年末調整で扶養控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。この申告書は、扶養控除の有無にかかわらず、給与所得者が必ず提出しなければならない重要な税務書類です。申告書には扶養親族の氏名、続柄、生年月日、所得額などの詳細情報を正確に記入する必要があります。
ダブルワークをしている従業員の場合は、主たる給与を受け取る1か所にのみ申告書を提出します。副業先には提出しないため、注意が必要です。また、年の途中で扶養親族の状況に変更があった場合は、速やかに異動届を提出することで、正確な控除を受けることができます。労務担当者は従業員に対して、記載内容の漏れや誤りがないよう丁寧にサポートすることが重要です。
扶養控除の適用要件と条件

扶養控除を受けるためには、扶養親族が満たすべき厳格な要件が定められています。これらの要件は税法に基づいて設定されており、一つでも満たさない場合は控除を受けることができません。主な要件として、年齢、所得金額、生計の状況、国籍・居住地などが挙げられます。特に所得要件については、2023年から段階的に改正が行われており、最新の基準を正確に把握することが重要です。
また、国外居住親族についても2023年1月から要件が変更されており、年齢制限や送金証明などの新たな条件が追加されています。これらの変更は、適正な税務申告を確保するために設けられたものであり、該当する場合は必要な書類の準備と提出が求められます。
年齢に関する要件
扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族が年末時点(12月31日)で16歳以上である必要があります。この年齢要件は、平成23年度の税制改正により導入されたもので、15歳以下の扶養親族は扶養控除の対象から除外されています。これは、子ども手当(現在の児童手当)の創設に伴い、重複する支援を整理するために行われた改正です。
16歳以上の年齢要件を満たす扶養親族は、さらに年齢に応じて控除額が区分されています。一般的な扶養親族から特定扶養親族、老人扶養親族まで、それぞれ異なる控除額が設定されており、扶養親族の年齢を正確に把握することが適切な控除を受けるために不可欠です。年齢の計算は、その年の12月31日現在の満年齢で行われます。
所得金額の制限
扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下であることが、扶養控除適用の重要な要件の一つです。給与所得のみの場合は、年収123万円以下に相当します。この所得制限は、扶養親族が経済的に独立していないことを税務上確認するために設けられています。所得金額の計算には、給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、雑所得など、すべての所得を合算する必要があります。
令和7年度税制改正により、扶養親族の年収上限が段階的に引き上げられる予定です。2025年からは年収上限が103万円から123万円に引き上げられ、特定扶養控除については年収上限が150万円まで拡大されます。さらに、子の年収が150万円を超えた場合でも188万円までは「特定親族特別控除」が新設されるなど、制度の大幅な見直しが行われています。
生計を一にする要件
「生計を一にする」とは、日常生活の資を共通にしていることを意味します。これは必ずしも同一の住所に居住していることを要求するものではなく、経済的な一体性があることが重要な判定基準となります。例えば、大学進学で子どもが親元を離れていても、親が学費や生活費を負担している場合は、生計を一にしていると認められます。
生計の一体性は、金銭的な援助の有無、生活費の負担状況、経済的な依存関係などを総合的に判断して認定されます。単に時々小遣いを渡している程度では生計を一にしているとは認められませんが、定期的かつ継続的な経済支援があれば、別居していても扶養関係は成立します。この要件の判定は実態に基づいて行われるため、具体的な支援状況を明確に説明できることが重要です。
国外居住親族の特別要件
2023年1月から、国外居住親族についての扶養控除要件が大幅に見直されました。新たな要件では、16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満で特定の条件を満たす人が対象となります。30歳以上70歳未満の国外居住親族については、留学生であることや障害者であること、扶養者から年間38万円以上の送金を受けていることなど、より厳格な要件が課されています。
これらの改正は、適正な扶養控除の適用を確保するために導入されたものです。国外居住親族を扶養控除の対象とする場合は、親族関係書類や送金関係書類の提出が義務付けられており、書類の翻訳や領事館での証明が必要になる場合もあります。該当する納税者は、必要な書類を事前に準備し、要件を満たしていることを適切に証明できるようにしておくことが重要です。
扶養控除の種類と控除額

扶養控除は扶養親族の年齢や状況に応じて、複数の区分に分かれています。それぞれの区分で控除額が異なるため、扶養親族の詳細な状況を正確に把握し、適切な控除区分を選択することが重要です。主な区分として、一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族があり、さらに老人扶養親族は同居の有無によって控除額が分かれています。
各控除区分の適用要件と控除額を正確に理解することで、最大限の税制メリットを受けることができます。また、令和7年度税制改正により、特定扶養控除の要件緩和や新たな控除制度の創設が予定されており、これらの変更点も併せて把握しておく必要があります。
一般の扶養控除
一般の扶養控除は、16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満の扶養親族に適用される控除です。控除額は38万円となっており、扶養控除の基本的な金額として位置づけられています。この年齢範囲には、高校生や大学を卒業した社会人になりたての子ども、働き盛りの兄弟姉妹などが含まれる可能性があります。
一般の扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の年間所得が48万円以下である必要があります。アルバイトやパートタイムの収入がある場合でも、年収123万円以下であれば給与所得控除を差し引いた後の所得金額が48万円以下となるため、扶養控除の対象となります。ただし、複数の所得がある場合は合算して判定するため、注意が必要です。
特定扶養控除
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族に対して適用される控除で、控除額は63万円と一般の扶養控除よりも25万円高く設定されています。この年齢層は大学生や専門学校生が多く、教育費の負担が重い時期であることを考慮して、より手厚い控除が設けられています。特定扶養控除は、子育て世代の経済的負担を軽減する重要な制度として機能しています。
令和7年度税制改正では、特定扶養控除について大幅な制度変更が予定されています。現行の年収103万円以下という所得要件が150万円以下まで緩和されるため、アルバイト収入が多い大学生でも扶養控除の対象となる可能性が広がります。さらに、年収が150万円を超えても188万円以下であれば「特定親族特別控除」の対象となり、段階的な控除を受けることができるようになります。
老人扶養控除
老人扶養控除は、70歳以上の扶養親族に適用される控除で、同居の有無によって控除額が異なります。同居老親等に該当する場合の控除額は58万円、その他の老人扶養親族の場合は48万円となっています。同居老親等とは、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、納税者またはその配偶者と常に同居している人を指します。
老人扶養控除の「同居」要件については、病気治療のための入院や老人ホームへの入所などは一時的な別居として扱われ、同居老親等の要件を満たすとされています。しかし、有料老人ホームや特別養護老人ホームなどへの長期入所の場合は、施設の性質や入所期間などを考慮して個別に判断されます。適切な控除を受けるためには、実際の居住状況を正確に把握しておくことが重要です。
障害者控除との併用
扶養親族が障害者に該当する場合は、扶養控除に加えて障害者控除も適用することができます。障害者控除は一般障害者で27万円、特別障害者で40万円、同居特別障害者で75万円の控除額となっています。これらの控除は扶養控除と併用可能であるため、該当する扶養親族がいる場合は大幅な税負担軽減効果が期待できます。
障害者控除の対象となる障害の範囲は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けている人のほか、65歳以上で市町村長等から障害者に準ずるものとして認定を受けている人も含まれます。また、年の途中で障害者となった場合でも、その年分から障害者控除の適用を受けることができるため、状況の変化があった場合は速やかに申告内容を更新することが重要です。
令和7年度税制改正の影響
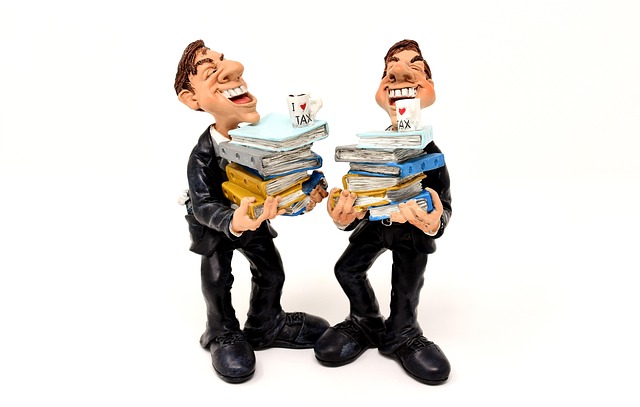
令和7年度税制改正では、扶養控除制度に関して大幅な見直しが行われています。これらの改正は、現代の働き方の多様化や学生のアルバイト収入の増加、社会情勢の変化に対応するために実施されるものです。主な改正点として、扶養親族の年収上限の引き上げ、特定扶養控除の要件緩和、新たな控除制度の創設などが挙げられます。
これらの改正により、従来は扶養控除の対象外となっていた多くの世帯が新たに控除を受けられるようになる一方で、制度の複雑化による理解の困難さや申告ミスの増加も懸念されています。企業の労務担当者や納税者自身が、改正内容を正確に理解し、適切に制度を活用することが重要です。
年収上限の引き上げ
2025年から実施される改正では、一般的な扶養親族の年収上限が103万円から123万円に引き上げられます。これにより、年収123万円以下(所得48万円以下)の扶養親族について、38万円の扶養控除を受けることができるようになります。この改正は、最低賃金の上昇やアルバイト・パートタイムの時給増加に対応するためのものです。
年収上限の引き上げは、特にアルバイトをしている大学生や高校生を持つ家庭に大きな影響を与えます。従来は年収103万円を超えると扶養控除の対象外となっていましたが、改正後は123万円まで扶養控除を継続して受けることができるため、学生自身の収入増加と家族の税負担軽減の両方を実現できるようになります。
特定扶養控除の要件緩和
特定扶養控除については、年収上限が大幅に緩和され、150万円以下まで拡大されます。この改正により、19歳以上23歳未満の扶養親族の年収が150万円以下であれば、63万円の特定扶養控除を受けることができるようになります。大学生のアルバイト収入が多様化する中で、より多くの世帯が控除を受けられるようになることが期待されています。
この要件緩和は、高等教育にかかる費用負担の軽減を目的としています。大学の学費や生活費の高騰により、学生自身がアルバイトで収入を得る必要性が高まっている現状を踏まえ、家族全体の経済的負担を軽減するための措置として導入されます。これにより、学業と就労の両立を支援する税制環境が整備されることになります。
特定親族特別控除の新設
令和7年度税制改正では、「特定親族特別控除」という新たな控除制度が創設されます。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族の年収が150万円を超えても188万円以下であれば適用される控除で、年収に応じて段階的に控除額が設定されます。この制度により、特定扶養控除の対象から外れた場合でも、一定の税負担軽減効果を維持することができます。
特定親族特別控除は、扶養控除の「崖効果」を緩和するために導入される制度です。従来は年収が上限を1円でも超えると控除が全額なくなってしまいましたが、新制度では段階的に控除額が減少するため、収入増加に対する税負担の急激な変化を抑制することができます。これにより、学生の就労意欲を阻害することなく、適切な税負担の実現が図られます。
制度変更に伴う注意点
税制改正に伴い、扶養親族が控除の対象から外れる場合には、新たな税負担が発生することになります。扶養親族自身の所得税や住民税の負担開始、社会保険料の負担、親の扶養控除の減少による税負担増加など、複合的な影響が生じる可能性があります。これらの変化を事前に把握し、家計への影響を適切に見積もることが重要です。
また、制度の複雑化により、申告ミスや控除の適用漏れが発生する可能性も高まります。企業の労務担当者は、従業員に対して制度変更の内容を分かりやすく説明し、正確な申告をサポートする体制を整備する必要があります。税務署や税理士などの専門家と連携し、適切な情報提供と相談体制の構築を図ることが求められています。
年末調整での実務的な取り扱い

年末調整における扶養控除の実務処理は、正確性と効率性の両方を求められる重要な業務です。企業の労務担当者は、従業員から提出される申告書の内容を適切に確認し、税法に基づいた正確な計算を行う必要があります。また、従業員に対する制度説明や書類作成支援も重要な役割となります。
実務処理においては、申告書の回収から内容確認、計算処理、結果通知まで、一連の流れを効率的に管理することが求められます。特に大規模な企業では、多数の従業員の申告を短期間で処理する必要があるため、システム化や標準化された手順の整備が不可欠です。
申告書の回収と確認方法
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の回収は、年末調整業務の出発点となる重要なプロセスです。回収時期については、通常10月から11月にかけて実施されることが多く、従業員に対して十分な記入時間を確保するとともに、年末調整の計算期限に間に合うよう計画的に進める必要があります。申告書の配布時には、記入要領や制度変更点について説明資料を併せて提供することが重要です。
申告書の内容確認においては、扶養親族の基本情報(氏名、続柄、生年月日、住所)の正確性、所得金額の妥当性、控除区分の適切性などを重点的にチェックします。特に前年から変更があった項目については、詳細な確認が必要です。記入漏れや明らかな誤りがある場合は、従業員に対して速やかに確認と修正を求め、正確な申告書の提出を促します。
扶養親族の所得確認
扶養親族の所得確認は、扶養控除の適用可否を判定する最も重要な作業の一つです。給与所得のみの場合は源泉徴収票により確認できますが、事業所得や不動産所得、雑所得などがある場合は、これらを合算した総所得金額で判定する必要があります。学生のアルバイト収入についても、複数の勤務先からの収入がある場合は、全ての収入を合計して判定します。
所得金額の確認においては、必要に応じて従業員に証明書類の提出を求めることもあります。特に自営業を営む扶養親族や、複数の収入源がある場合は、確定申告書の控えや所得証明書などによる確認が重要です。また、年の途中で退職した扶養親族については、退職時の源泉徴収票により年間の所得金額を確認する必要があります。
システムへの入力と計算処理
申告書の内容確認が完了したら、給与計算システムへの入力作業を行います。扶養親族の基本情報、控除区分、適用開始時期などを正確に入力し、システムによる自動計算の基礎データを整備します。入力作業においては、転記ミスや入力漏れを防ぐため、複数人によるチェック体制や、システムの検証機能を活用することが重要です。
計算処理においては、扶養控除額の自動計算だけでなく、他の所得控除や税額控除との関係も適切に処理される必要があります。特に基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などとの合計額が、正確に所得税および住民税の計算に反映されることを確認します。計算結果については、前年との比較や類似ケースとの比較により、妥当性をチェックすることも重要です。
従業員への結果通知と説明
年末調整の計算が完了したら、従業員に対して結果を通知します。源泉徴収票の交付と併せて、扶養控除の適用状況や控除額、税額の増減理由などについて、分かりやすく説明することが重要です。特に前年と比較して大きな変動があった場合や、制度改正の影響がある場合は、詳細な説明を行い、従業員の理解を促進します。
また、年末調整で扶養控除の適用を受けられなかった従業員や、年の途中で扶養親族に変更があった従業員については、確定申告による対応方法についても案内する必要があります。税務署への相談方法や必要書類、申告期限などの情報を提供し、従業員が適切に税務手続きを行えるよう支援することが企業の責務となります。
確定申告での扶養控除申請

年末調整で扶養控除の申請ができなかった場合や、年末調整後に扶養親族の状況に変更があった場合は、確定申告によって扶養控除を申請することができます。確定申告での扶養控除申請は、年末調整とは異なる手続きや注意点があるため、正確な理解と適切な準備が必要です。また、確定申告では年末調整よりも詳細な書類の提出や証明が求められる場合があります。
確定申告による扶養控除の申請は、過年度分の修正申告や、複雑な家族状況の場合にも活用できる重要な制度です。適切に申告することで、本来受けられるべき税制上のメリットを確実に享受することができます。
確定申告が必要なケース
確定申告で扶養控除を申請する必要があるケースとして、年末調整の対象外となる給与所得者や自営業者、年の途中で退職した人などが挙げられます。また、年末調整時点では扶養要件を満たしていなかったが、年末までに要件を満たすようになった場合や、申告書の提出を忘れていた場合なども確定申告による対応が必要です。
複数の勤務先から給与を受けている場合や、給与以外の所得がある場合も、確定申告での扶養控除申請が必要となることがあります。特にフリーランスや副業収入がある人、不動産所得や株式の譲渡所得がある人などは、年末調整だけでは完結しないため、確定申告において全ての所得と控除を総合的に申告する必要があります。
申告書の作成方法
確定申告書における扶養控除の記入は、申告書Bの所得控除の欄に行います。扶養親族の氏名、続柄、生年月日、所得金額を正確に記入し、控除区分(一般、特定、老人)に応じた控除額を計算します。記入にあたっては、扶養親族の所得を証明する書類(源泉徴収票、支払調書、帳簿など)を事前に準備し、正確な金額を把握しておくことが重要です。
e-Taxを利用した電子申告では、扶養親族の情報を入力すると自動的に控除額が計算されるため、計算ミスを防ぐことができます。また、過年度の申告データを引き継ぐことも可能なため、継続して扶養している親族についてはデータの転記により効率的に申告書を作成できます。ただし、扶養親族の状況に変更がないか毎年確認することが必要です。
必要書類と証明資料
確定申告での扶養控除申請においては、扶養親族の所得を証明する書類の提出が求められる場合があります。給与所得者の扶養親族については源泉徴収票、自営業者については収支内訳書や青色申告決算書、年金受給者については公的年金等の源泉徴収票などが必要です。これらの書類は申告書と併せて提出するか、税務署での確認に備えて保管しておきます。
国外居住親族を扶養控除の対象とする場合は、親族関係書類(戸籍謄本、出生証明書など)と送金関係書類(外国送金依頼書、クレジットカード使用明細書など)の提出が義務付けられています。これらの書類が外国語で作成されている場合は、翻訳文の添付も必要です。適切な書類の準備には時間がかかるため、早めの準備が重要です。
申告期限と還付手続き
確定申告の期限は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。この期間内に申告書を提出し、扶養控除による還付を受けることができます。還付申告については、2月16日より前でも1月1日から受け付けており、早期に申告することで還付金の早期受領が可能です。また、還付申告については5年間の時効があるため、過去5年分までさかのぼって申告することができます。
還付金の受領方法は、銀行振込または郵便局での受取から選択できます。e-Taxによる電子申告の場合は処理が迅速で、通常2〜3週間程度で還付されます。書面申告の場合は1〜2か月程度要することが一般的です。還付金の受領確認は、国税庁ホームページの「還付金の処理状況」で確認することができるため、適宜確認することをお勧めします。
まとめ
年末調整における扶養控除は、家族を扶養している納税者にとって重要な税負担軽減制度です。16歳以上の扶養親族がいる場合、適切な要件を満たすことで最大63万円(特定扶養親族の場合)の所得控除を受けることができ、所得税や住民税の大幅な軽減効果が期待できます。制度を適切に活用するためには、扶養親族の年齢、所得金額、生計の状況などの要件を正確に把握し、必要な申告手続きを確実に行うことが不可欠です。
特に令和7年度税制改正により、扶養控除制度は大幅な見直しが行われています。年収上限の引き上げや特定扶養控除の要件緩和、新たな控除制度の創設など、多くの世帯にとって有利な変更が実施されます。これらの制度変更を適切に理解し、活用することで、より効果的な税負担軽減を実現することができるでしょう。企業の労務担当者や納税者自身が制度の詳細を把握し、正確な申告を行うことが、適切な税務処理と税負担の最適化につながります。
よくある質問
扶養控除の対象となる親族の範囲は?
扶養控除の対象となる「控除対象扶養親族」は、配偶者以外の直系血族および兄弟姉妹、さらには一定の親族関係にある者まで含まれます。ただし、扶養親族は納税者と「生計を一にする」必要があります。これは同居を意味するものではなく、経済的な支援関係があることを指します。
扶養控除を受けるための要件は何ですか?
扶養控除を受けるためには、扶養親族が年齢、所得金額、生計の状況、国籍・居住地など、税法に基づいて定められた厳格な要件を満たす必要があります。特に所得要件については、2023年から段階的な改正が行われており、最新の基準を把握することが重要です。
年末調整で扶養控除を受けるには何をすればよいですか?
年末調整で扶養控除を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を勤務先に提出する必要があります。この申告書には扶養親族の詳細情報を正確に記入し、記載内容の漏れや誤りがないよう注意が必要です。
扶養控除の種類と控除額はどうなっていますか?
扶養控除には、一般の扶養控除(38万円)、特定扶養控除(63万円)、老人扶養控除(48万円/58万円)などがあり、扶養親族の年齢や状況に応じて控除額が異なります。また、令和7年度の税制改正により、特定扶養控除の要件緩和や新たな控除制度の創設が予定されています。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


