目次
はじめに
確定申告における扶養控除は、納税者の負担を軽減する重要な所得控除制度の一つです。扶養親族を持つ方にとって、この制度を正しく理解し活用することで、所得税や住民税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
扶養控除の基本的な仕組み
扶養控除は、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除制度です。この制度により、課税所得が減少し、年末調整や確定申告において所得税・住民税の納税額を抑えることができます。
扶養控除を適用することで、納税者の事情に配慮して税負担を軽減する効果があります。特に複数の扶養親族がいる家庭では、その経済的効果は非常に大きなものとなるでしょう。
令和7年度税制改正の影響
令和7年度の税制改正により、扶養控除に関する要件が大幅に見直されました。特に注目すべきは、扶養親族の所得要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられたことです。これにより、より多くの親族が扶養控除の対象となる可能性が広がります。
また、特定親族特別控除の新設や基礎控除額の見直しなど、扶養控除に関連する制度全体が大幅に改正されています。これらの改正は原則として令和7年分以後の所得税について適用されるため、確定申告を行う際は新しい制度を理解しておくことが重要です。
確定申告での重要性
扶養控除は会社員の場合は年末調整で、個人事業主や年末調整の対象外の会社員は確定申告で適用を受けることができます。特に確定申告では、扶養控除の適用要件を正確に確認し、適切な控除を受けることが重要です。
確定申告の際は所得税の申告書に関連事項を記載する必要があり、親族の年齢や所得要件などの詳細な情報を正確に把握しておく必要があります。これにより、適切な税務処理を行うことができるでしょう。
扶養控除の基本要件

扶養控除を受けるためには、いくつかの基本要件を満たす必要があります。これらの要件を正確に理解することが、適切な扶養控除の適用につながります。
年齢要件
扶養控除の基本的な年齢要件は、16歳以上であることです。この年齢制限により、15歳以下の子どもについては扶養控除の対象外となっています。ただし、16歳未満の子どもについても住民税の扶養控除は適用される場合があります。
非居住者の場合は、年齢要件がより複雑になります。16歳以上30歳未満、70歳以上、または30歳以上70歳未満で一定の条件を満たす必要があります。海外に住む親族を扶養親族とする場合は、これらの特別な要件を慎重に確認する必要があります。
親族の範囲
扶養控除の対象となる親族の範囲は、6親等内の血族や3親等内の姻族と定められています。これには、自分の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫などの血族のほか、配偶者の両親や兄弟姉妹などの姻族も含まれます。
また、里子や養護老人についても扶養控除の対象となります。ただし、配偶者については扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるため、扶養控除の対象にはなりません。この点は非常に重要な区別です。
所得要件
令和7年度税制改正により、扶養親族の所得要件は年間所得58万円以下に引き上げられました。これまでは48万円以下という制限でしたが、この改正により扶養控除の対象となる親族の範囲が拡大されています。
所得の計算においては、給与所得者の場合は給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額が所得となります。例えば、給与収入が150万円の場合でも、給与所得控除を適用した後の所得が58万円以下であれば扶養控除の対象となります。
生計を一にする要件
扶養控除を受けるためには、扶養親族と「生計を一にしている」ことが必要です。これは必ずしも同居している必要はなく、経済的に支援している関係であることが重要です。例えば、地方の両親に仕送りをしている場合なども、生計を一にしているとみなされます。
同居老親等の場合は、病気のため入院していても同居とみなされますが、老人ホームに入所している場合は同居とはみなされません。この微妙な違いが控除額に影響するため、実際の生活状況を正確に把握しておくことが重要です。
扶養控除の種類と控除額

扶養控除は扶養親族の年齢や状況に応じて異なる区分があり、それぞれ控除額が設定されています。これらの区分を正確に理解することで、適切な控除を受けることができます。
一般の控除対象扶養親族
16歳以上19歳未満、および23歳以上70歳未満の扶養親族は「一般の控除対象扶養親族」に分類されます。この区分の控除額は38万円(住民税は33万円)となっています。最も基本的な扶養控除の区分であり、多くの扶養親族がこの分類に該当します。
一般の控除対象扶養親族の控除を受けることで、年間38万円分の所得控除を受けることができます。所得税率が10%の場合、実際の税負担軽減効果は約3万8千円となり、家計にとって大きなメリットとなります。
特定扶養親族
19歳以上23歳未満の扶養親族は「特定扶養親族」として扱われ、控除額は63万円(住民税は45万円)と一般の扶養親族よりも大幅に高く設定されています。この年齢層は大学生等の高等教育を受けている時期に該当し、教育費負担が大きいことを考慮した制度設計となっています。
令和7年度税制改正により、特定扶養控除の対象となる子どもの年収上限が150万円まで拡大されました。これにより、アルバイト等で一定の収入を得ている学生でも、扶養控除の対象となる可能性が高まっています。
老人扶養親族
70歳以上の扶養親族は「老人扶養親族」として分類され、48万円の控除を受けることができます。高齢者の扶養には医療費や介護費用などの負担が伴うことを考慮し、一般の扶養親族よりも高い控除額が設定されています。
老人扶養親族の中でも、納税者や配偶者の直系尊属(両親、祖父母等)で同居している場合は「同居老親等」として扱われ、さらに10万円が加算されて58万円の控除となります。この同居加算により、親の介護等で同居している家庭の税負担が大幅に軽減されます。
扶養控除額の比較表
| 区分 | 年齢 | 所得税控除額 | 住民税控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等 | 70歳以上(同居の直系尊属) | 58万円 | 45万円 |
特定親族特別控除の新設
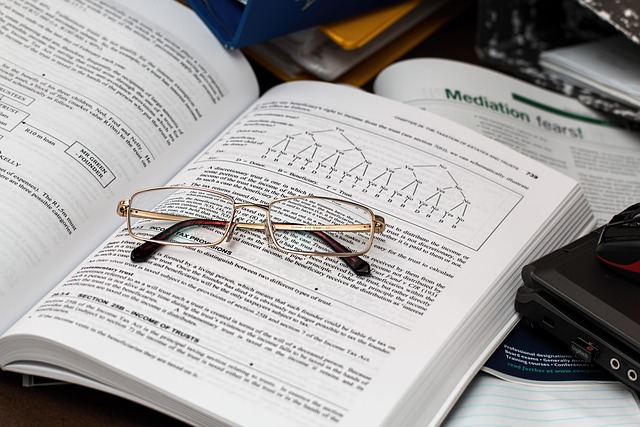
令和7年度税制改正の目玉の一つが、特定親族特別控除の新設です。この新しい控除制度は、従来の扶養控除制度の枠組みを拡張し、より柔軟な税負担軽減を実現するものです。
特定親族特別控除の概要
特定親族特別控除は、子どもの年収が150万円を超えても、世帯の手取りを減らさずに済むよう設計された新しい控除制度です。これまでは扶養控除の所得要件を超えると控除が全くなくなってしまいましたが、この制度により段階的な控除が可能になります。
この控除の創設により、学生が就職活動やインターンシップ、アルバイトなどで収入を得る場合でも、家庭の税負担が急激に増加することを防ぐことができます。特に高等教育を受けている期間の経済的負担軽減に大きく寄与する制度といえるでしょう。
適用要件と対象者
特定親族特別控除の対象となるのは、主に19歳から22歳の子どもで、年収が150万円を超える場合です。従来の特定扶養控除の対象から外れる所得水準の親族に対して、新たな控除の枠組みを提供します。
この控除を受けるためには、従来の扶養控除と同様に生計を一にしていることや、その他の要件を満たす必要があります。また、確定申告や年末調整の際には、適切な申告書の提出と記載が必要となります。
控除額の算定方法
特定親族特別控除の控除額は、扶養親族の所得金額に応じて段階的に設定されています。所得が一定額を超えると控除額が逓減する仕組みとなっており、従来の扶養控除のように急激に控除がなくなることがありません。
この段階的な控除額の設定により、扶養親族の所得が増加しても税負担の急激な変化を避けることができます。家庭の経済計画を立てる上でも、より予測しやすい税制となったといえるでしょう。
従来制度との比較
従来の扶養控除制度では、扶養親族の所得が48万円(改正後58万円)を1円でも超えると、控除が全くなくなってしまうという問題がありました。特定親族特別控除の新設により、この「所得の崖」問題が大幅に改善されます。
新制度では、扶養親族の所得が増加しても控除額が段階的に減少するため、働き方の選択肢が広がります。特に学生の場合、学業と両立しながら働く際の所得制限を気にすることが少なくなり、より柔軟な働き方が可能になるでしょう。
確定申告での扶養控除の手続き

確定申告において扶養控除を適用するためには、適切な手続きと正確な記載が必要です。申告書の作成から提出まで、各段階での注意点を理解しておくことが重要です。
申告書への記載方法
確定申告書における扶養控除の記載は、所得税申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄で行います。扶養親族の氏名、続柄、生年月日、所得金額などの詳細な情報を正確に記入する必要があります。
特に重要なのは、扶養親族の所得金額の計算です。給与所得者の場合は源泉徴収票を基に、事業所得者の場合は収支内訳書等を参考に正確な所得金額を算定します。この計算を誤ると扶養控除の適用に影響が出る可能性があるため、慎重に行う必要があります。
必要書類の準備
扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の所得を証明する書類の準備が必要です。給与所得者の場合は源泉徴収票、年金受給者の場合は年金の源泉徴収票、事業所得者の場合は収支内訳書などが該当します。
非居住者の扶養親族がいる場合は、さらに送金関係書類や親族関係書類などの追加書類が必要となります。これらの書類は事前に準備し、申告期限に余裕を持って手続きを進めることが重要です。
年末調整との関係
会社員の場合、通常は年末調整で扶養控除の適用を受けますが、年末調整で適用できなかった控除や、年末調整後に扶養親族の状況が変わった場合は確定申告で修正することができます。
年末調整では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出することで扶養控除を適用しますが、記載内容に誤りがあった場合や、扶養親族の所得が確定後に要件を満たさなくなった場合は、確定申告での修正申告が必要となります。
電子申告での注意点
e-Taxを利用した電子申告の場合、扶養控除に関する入力項目が複数に分かれています。扶養親族の基本情報、所得情報、控除区分などを順次入力していく必要があり、入力ミスを避けるため各項目を慎重に確認することが重要です。
また、電子申告では添付書類の提出方法が書面申告と異なる場合があります。扶養控除に関する証明書類についても、電子データでの提出が可能な場合と、別途郵送が必要な場合があるため、事前に確認しておくことが必要です。
よくある間違いと注意点

扶養控除の申告においては、制度の複雑さから様々な間違いが発生しがちです。これらの間違いを事前に理解し、適切な申告を行うことが重要です。
所得計算の間違い
最も多い間違いの一つが、扶養親族の所得計算です。収入と所得の区別ができていない場合や、各種控除の適用を忘れてしまう場合があります。給与所得者の場合、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が所得となることを正確に理解する必要があります。
また、複数の所得がある場合の合計所得金額の計算も間違いやすいポイントです。給与所得、年金所得、事業所得など複数の所得がある場合は、それぞれを正確に計算し合算する必要があります。この計算を誤ると扶養控除の要件判定に影響が出てしまいます。
重複適用の問題
同一の扶養親族について、複数の納税者が扶養控除を適用してしまうケースがあります。例えば、夫婦共働きの場合に、同じ子どもについて夫婦それぞれが扶養控除を適用してしまうことがあります。扶養控除は一人の扶養親族につき一人の納税者しか適用できません。
この問題を避けるためには、家族内で事前に誰が誰の扶養控除を適用するかを明確に決めておく必要があります。所得の高い方が扶養控除を適用した方が節税効果が高い場合が多いため、家族全体の税負担を考慮して決定することが重要です。
配偶者との混同
配偶者について扶養控除を適用してしまう間違いも見受けられます。配偶者については扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるため、扶養控除の対象にはなりません。この区別を正確に理解しておくことが重要です。
配偶者控除と配偶者特別控除は、扶養控除とは別の制度であり、適用要件や控除額も異なります。配偶者の所得金額に応じてどの控除が適用されるかを正確に判定し、適切な申告を行う必要があります。
非居住者の扶養親族の取扱い
海外に住む親族を扶養親族とする場合の取扱いは特に複雑で、間違いが発生しやすい分野です。非居住者の扶養親族については、年齢要件や送金要件など、居住者とは異なる特別な要件があります。
また、必要な添付書類も多く、親族関係書類や送金関係書類などの準備が必要です。これらの書類は外国語で作成されている場合もあり、翻訳が必要な場合もあります。非居住者の扶養親族がいる場合は、事前に詳細な要件を確認し、必要書類を漏れなく準備することが重要です。
まとめ
扶養控除は、確定申告において重要な所得控除の一つであり、適切に活用することで大幅な税負担軽減を実現できます。令和7年度税制改正により、所得要件の緩和や特定親族特別控除の新設など、制度が大幅に改善され、より多くの方が恩恵を受けられるようになりました。
扶養控除を正しく適用するためには、扶養親族の年齢、所得、生計を一にする要件などの基本要件を正確に理解することが不可欠です。また、一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族といった区分ごとの控除額の違いを把握し、適切な申告を行うことが重要です。確定申告の際は、必要書類を漏れなく準備し、申告書への記載は慎重に行い、制度を最大限活用して適切な税務処理を実現しましょう。
よくある質問
扶養控除の対象となる親族の範囲は?
p. 扶養控除の対象となる親族の範囲は、6親等内の血族や3親等内の姻族と定められています。自分の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫などの血族のほか、配偶者の両親や兄弟姉妹などの姻族も含まれます。また、里子や養護老人についても扶養控除の対象となります。ただし、配偶者については扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されます。
扶養控除の要件には何があるのですか?
p. 扶養控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。年齢要件として16歳以上であること、所得要件として年間所得が58万円以下であること、生計を一にしていることなどが主な要件です。扶養親族の年齢や状況に応じて、一般の扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族など、さまざまな区分があり、それぞれ控除額が設定されています。
扶養控除の手続きはどのように行うのですか?
p. 確定申告において扶養控除を適用するためには、所得税申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄に扶養親族の詳細情報を正確に記入する必要があります。扶養親族の氏名、続柄、生年月日、所得金額などを詳細に記載し、必要書類も事前に準備しておくことが重要です。特に扶養親族の所得計算は慎重に行う必要があります。電子申告の場合は、各項目を順次入力し、添付書類の提出方法にも注意が必要です。
新設された「特定親族特別控除」とはどのような制度ですか?
p. 令和7年度税制改正により新設された「特定親族特別控除」は、従来の扶養控除制度を拡張した制度です。この制度では、扶養親族の所得が150万円を超えても段階的な控除が可能となり、急激な税負担の増加を避けることができます。特に大学生などの高等教育を受けている期間の経済的負担軽減に寄与する制度となっています。従来の扶養控除では所得が一定額を超えると控除がなくなっていた問題が改善されました。

 ご相談はこちらから
ご相談はこちらから


